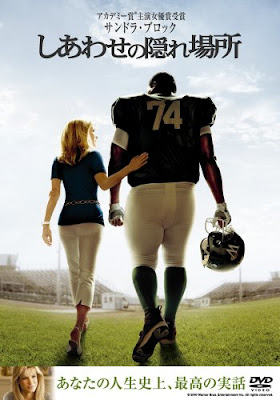「ザ・マスター」(12年米)。世界三大映画祭の監督賞を制覇した(wiki)とあった。
どこがいいのかわからない。半分も見ないうちに飽きてしまって、こんなに有名な映画なんだから、きっとこれからの話の展開が面白いのかもとか、鈍感私が感じることができないなにか深淵な背景があるのかもと、いくつかの映画評をチェックして
「オモシロイとこ探し」しながら最後まで付き合ったが、それでもさっぱり。砂の女と添い寝するラストシーンまでワタシの理解力を超えていた。
主人公の精神を病んだ男を演じたホアキン・フェニックスも、カリスマ男役のフィリップ・シーモア・ホフマンもほかのたくさんの映画ではあんなにイキイキ、悪役らしくしていたのに、ふたりとも怪しげな酒に飲まれた酔っ払い。酔っ払いが嫌いだからそう思うのだろうが、映画の中の二人の酔っ払いは、箴言ともとれるかもしれないさっぱりわからないたわごとを延々と繰り返す。シラフでも繰り返される議論や感情の沸騰は、オトナのケンカの席に居合わせてしまったように、居心地の悪さを感じてしまうのだ。
楽しさや悲しみや怒りの共感のない映画で、残り少ない時間を割くのは時間がもったいない気がする。一歩下がって、この映画に共感を覚えることができない自分のアタマの悪さや理解力のなさや、感性の鈍さを認めるとしても、ワタシのそれはこれから改善されることはないのだから、どんなに前評判が良くたくさんの賞を総なめにした作品でも、ごめんだ。
「マルホランド・ドライブ」(01年米仏)は巨匠デビット・リンチ監督の傑作とされている。もしかしたら、と見ることをずっと楽しみにしていたのだけど、
「やはり」ダメだった。ナオミ・ワッツも大根。作品に恵まれていないとはも思うが、
「21グラム」(03年)ではドキドキするくらい、日本映画の二番煎じの
「ザ・リング」(03年米)でさえあんなに魅力的だったのに。
リンチ監督の
「ツイン・ピークス」(90年テレビドラマ、92年米映画)、
「イレーザー・ヘッド」(76年米)も世界中の多くの知識人を大ファンにしたが、カルトを楽しむ度量の広さも小難しい作品をわかったフリをして楽しむことも、知識人の仲間にはいれないワタシにはできなかった。
 「チャイルド44 森に消えた子供たち」
「チャイルド44 森に消えた子供たち」(15年米)
「あの」リドリー・スコット製作だが、暗さ以外に彼らしいところのない映画、クヤシイ。スウェーデンの監督ダニエル・エスピノーザの力不足か。これだけの原作(トム・ロブ・スミス
「チャイルド44」09年版
「このミステリーがすごい!」海外編第1位)とのフレコミだったから、結局最後まで見てしまったが、もっとなんとかならなかったかとも思う。
主人公の国家保安省の捜査官の役、トム・ハーディーは、
「マッドマックス 怒りのデス・ロード」(15年米)や
「レヴェナント: 蘇えりし者」(15年米)、
「欲望のバージニア」(12年米)<
秀作-サウンドトラックだけでも聞く価値あり>のニヒルなタフガイさもなく、なんともとらえどころのない演技。ステキだったのは
「欲望の・・」と同じカリアゲ7・3の髪型が決まっていたことだけ。トム・ハーディーはこの髪型が好きらしい。
その妻を演じたスウェーデン女優ノオミ・ラパスは
「ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女」(09年スウェーデン)などのミレニアムシリーズの魅力的なシタタカ女とはうって変わって、これも何を考えているのかわからない役つくりとなった。愛していると言いながらそれが伝わってこない女優に用はない。大ファンのゲイリー・オールドマンの扱いもゼンゼン気に入らなかった、残念。オールドマンを使うのなら
「レオン」(94年仏米)でジャン・レノに手榴弾で吹っ飛ばされるのを観客が喜んで見るくらいのカリスマ性を持たせてほしかった。主人公の上司役のフランスの名優ヴァンサン・カッセルだけが、いつものように冷酷無比でハマっていた。
ただ、ひたすらに旧ソ連の秘密警察の横暴さと底知れぬ怖さを強調したような映画になってしまったが、たぶん原作の意図とは違うと思う。仮に、そのステレオタイプの横暴さや怖さがホンモノだったとしてもロシア文化省が、本作について”史実を歪めている”と非難したとのこと、ふむふむ、さもありなん。内なる醜さを突き付けられるというのはつらかろう。とはいえ、権力の暗い面ばかりを見せたい反ロシアキャンペーン映画なら、ハッピーエンドなんかにしてほしくなかった。
ワタシは無類の映画好き。しかし、映画は面白いか、ドキドキするか、心を打つか、なにかの引き金になるか、好きな俳優、特に好きな女優が出ているか、ストーリーに共感するか、音楽がいいか、などなどワタシの好みじゃないと。
 「恋するフォーチュンクッキー」「365日の紙飛行機」「ヘビーローテーション」がマイベストかな。「恋する・・は」前奏が始まったら、カラダが自然にリズムをとっている。
「恋するフォーチュンクッキー」「365日の紙飛行機」「ヘビーローテーション」がマイベストかな。「恋する・・は」前奏が始まったら、カラダが自然にリズムをとっている。 ドリカムは美和ちゃんの元気+シットリ情感で、誰かに愛されているような気がするから不思議だ。「うれしい!たのしい!大好き!」「LOVE LOVE LOVE」「晴れたらいいね」とかね。
ドリカムは美和ちゃんの元気+シットリ情感で、誰かに愛されているような気がするから不思議だ。「うれしい!たのしい!大好き!」「LOVE LOVE LOVE」「晴れたらいいね」とかね。